セントラリティはニュージーランドに本拠地を置くプロジェクト
まず、セントラリティはニュージーランドに本拠地を置くプロジェクトで、オークランド(ニュージーランド)、ロンドン、メルボルン(オーストラリア)に合計75名以上のメンバーがいる(公式サイト参照)。
パートナー企業/プロジェクトも豊富で、有名な仮想通貨ではEthereum系のSingularDTV(Consensysがプロデュースするプロジェクト)と提携している。

セントラリティの提携企業/プロジェクト
CEOがアーロン・マクドナルド氏、チェアマンがロジャー・スミス氏だ。

セントラリティは分散型アプリケーションのプラットフォーム
さて、ここからが本題だ。セントラリティとはいったいどういう仮想通貨なのか。
一言で言うと、セントラリティは分散型アプリケーション(DApps)のプラットフォームを目指すプロジェクトだ。つまり、先述のSingularDTVや、或いはOmiseGoやAugurのようにEthereumのプラットフォーム上で動作する仮想通貨ではなく、まさにEthereum、或いはADA、NEO、LISK、WAVESのように、独自ブロックチェーンを形成し、セントラリティ自身がプラットフォームとなるプロジェクトだ。
またセントラリティは、自身のプラットフォーム上で様々な分散型アプリケーションを動作させることができる設計となっている。
分散型アプリケーションとは?
まず平たくアプリケーションという言葉を捉えてみると、我々が日頃使うもので身近なのはスマートフォンのアプリケーションだ。分散型アプリケーションもスマホのアプリと同じイメージを持っていただいて差し支えない。ただし、”分散型”という言葉がスマホアプリとの違いを特徴付けている。
分散型アプリケーションとは、
・ オープンソースで、中央によるコントロールがなく、分散型ブロックチェーン上で自動的に動作するもの
・ 独自のトークンがあり、アプリの利用料やリワードは、トークンの受け渡しで達成され、トークンは流通可能であること
・アプリケーションの改善は、マーケットやユーザーの要望に従い、改善作業は必ずユーザーの合意に基づくこと(つまり中央の主体が決めるのではない)
という特徴を満たすものだ。つまり平たく言うと、ブロックチェーン上で自動的に動作し、中央による管理がなく、トークンによって利用が可能になるものだ。
そういう意味では、仮想通貨全般がそもそもDAppsだという言い方もできるが、例えばリップルは上記の特徴を満たさないためDAppsとは言えない。ビットコインは今でも管理主体がないため、DAppsと言えそうだが、EthereumはEthereum Foundationが開発組織としてガッチリと管理しているため、厳密にはDAppsとは言えないかもしれない。
とは言え、基本的に上記の条件をある程度満たす仮想通貨はDAppsと呼ばれ、中でもプラットフォーム上で動作する仮想通貨は分散型アプリケーションと呼ばれる。(例:SingularDTV、Augur、Gnosis、OmiseGo、Status、その他多数)
というわけで、セントラリティ上で動作する分散型アプリケーション(DApps)とは、つまりセントラリティ上で動作する仮想通貨のことだ。
セントラリティはDAppsを利用しやすいプラットフォーム
では、セントラリティの特徴を捉えるために、他の類似のプラットフォームとの比較を行ってみたい。
例えばEthereumを見てみると、Ethereumもプラットフォーム型の仮想通貨だ。つまり、Ethereumプラットフォーム上で様々なDAppsを動作させることができる。Ethereumだけでなく、LISKやNEOといった仮想通貨も同様のことができる。(無論、それぞれ細かな違いや特徴が存在する)
ではセントラリティが他のプラットフォームに比べて特徴的なのは何か?それは、分散型アプリケーションの運用に特化しているという点だろう。
セントラリティの仕組み

セントラリティのホワイトペーパー13ページ目には、以下のように書かれている。
「セントラリティプラットフォームはDApps(アプリ)の基盤となるものを提供する。各DAppsにおいて発行されるトークンは必ず一定量セントラリティ側に寄与され、セントラリティはこれをプラットフォーム強化のために使用し、技術者たちはセントラリティ上で使われるモジュールを随時開発し、各DAppsはそれらを購入することができる。」
ここで言うモジュールとは、セントラリティでDAppsを構築するときに使える部品のようなものだ。セントラリティでは、DApps(アプリ)開発者が、セントラリティに予め用意された”部品”を使って簡単にDAppsを作れるように設計されている。(この時DApps開発者は、”部品”をCENNZトークンで購入することになる)

「セントラリティに接続されたDApps。各DAppsはCENNZトークンを用いてアプリに必要なモジュール(部品)を購入し、ユーザー、データ、内容、事業者、そしてシステム内のトークンと接続される。」

「それぞれのDAppsは異なるアプリではあるが、連携して動作し、ユーザー、データ、内容、事業者を獲得する。セントラリティプラットフォーム全体で使われるスマートコントラクトが、異なる企業(DAppsの運営元)同士が信頼し合える状態を作り上げる。」

「各DAppsは、そのDApps自身の事業や顧客サービスに100%集中でき、セントラリティは根幹となる技術やデザインに注力する。」
このように、セントラリティでは、EthereumやNEOといった他のプラットフォームに比べDAppsを構築しやすい設計となっており、まさにWindowsのように、誰もが使いやすいアプリのプラットフォームとなることを目指している。
Ethereumとセントラリティの違い
では、例としてEthereumとセントラリティの違いをまとめてみよう。
・セントラリティではDAppsを構成するモジュール(部品)が提供される(Ethereumにはない)
・モジュールを利用することで、開発者は容易にDAppsを構築可能(Ethereum上でDAppsを構築するのは簡単ではない)
・モジュールはセントラリティ内での統一規格に基づいているため、各DAppsはユーザーやデータの共有が可能(Ethereumでは各DAppsの仕様が完全に異なるため横の繋がりはない)

ユーザーから見たセントラリティ
セントラリティの特徴が分かったところで、ではユーザーにとっては何が良いのだろうか。セントラリティのホワイトペーパー15ページ目からこの辺りのことが書かれている。
アプリ(DApps)毎にユーザー登録する必要がない
まず、各アプリ(DApps)でシステムの規格が統一されており、データを共有することができるので、ユーザーはアプリ毎にアカウントを作ったり、インストールしたりする必要がない。
以下のような例が挙げられている。
Belong(割引券やポイントを配布できるアプリ)というアプリで、あるイベントの割引券を得た人がいたとして、するとBelongは自動的に他のセントラリティアプリであるUShare(交通機関を案内してくれるアプリ)に接続し、アプリ間の接続ツールが作動して、UShareがBelongのイベント場所までの交通機関を提示することが可能になる。
ユーザーがこれを実行に移すと、UShareアプリが即座にインストールされ、ユーザーデータやウォレット情報が自動的に同期される。
こうしてユーザーは、UShareを自分でインストールしたり、登録したり、目的地の住所を入力したりといった手間をかけることなく、同アプリを使って目的地まで到達することができる。
BelongとUShareはスマートコントラクトによりこの同期作業を行なっている。

ICOで100億円以上の資金を調達
以上のような特徴がセントラリティの全てではないが、根幹となる部分だと言えよう。他のプラットフォーム系仮想通貨との違いや、セントラリティの良さが垣間見えただろうか。
セントラリティには、先ほどご紹介したBelongやUShareのようなアプリが合計で10以上既に存在し、プロダクトのベースは出来上がっていると言える。
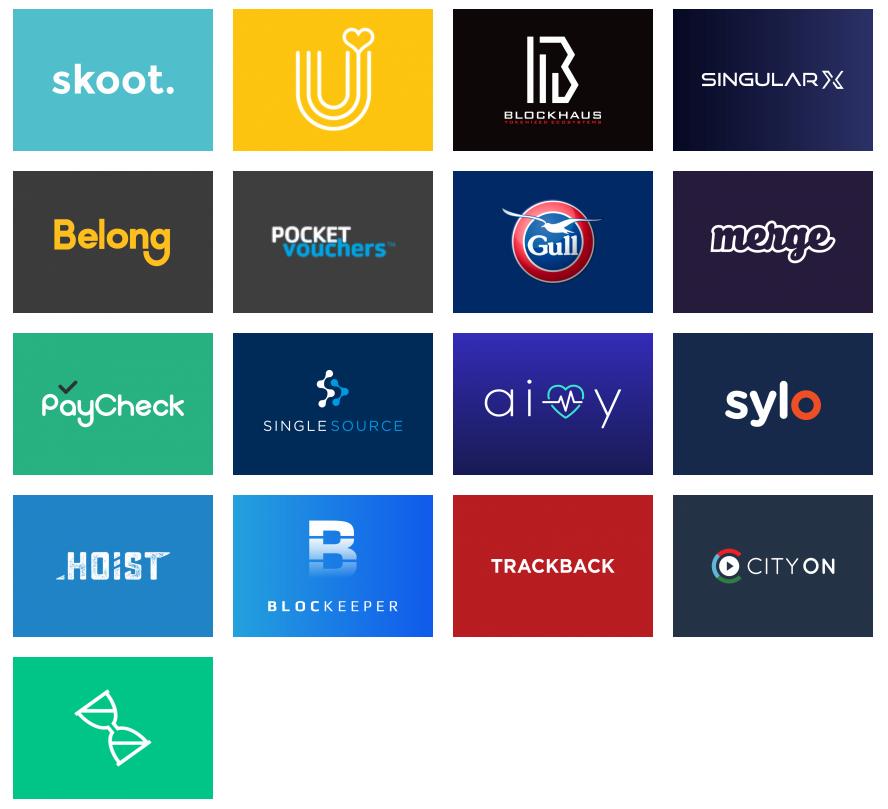
1月15日に行われたICOでは100億円以上の調達に成功し、またそれ以前のプレセールでも40,000ETH(現在の時価で約50億円)を調達しており、幸先は良さそうだ。
また、セントラリティはニュージーランド政府から3年間にわたって15億円に上る研究助成金を受ける。SingularDTV や Blockhaus AG というブロックチェーンプロジェクトとも提携している。
セントラリティは本格始動してまだ半年ほどだと言うが、そのポテンシャルが評価され、上記のような先行例を築くに至ったのだろう。
セントラリティのホワイトペーパー冒頭には、テクノロジーの分野でも経済格差が生まれていることが指摘されている。つまり、どれだけ良いアイディアや実行力をもったスタートアップでも、既存の巨大IT企業には敵わず、なかなか陽の目を見ることができないということだ。
セントラリティは、ブロックチェーンという革新的な技術でプラットフォームを構築し、新しいアイディアや技術がユーザーに届きやすく、新たな事業がきちんと評価される形態を作ろうとしている。
様々なアプリが独自のサービスを構築し、アプリ間でシームレスに協働することで一大サービスを作り出す。そんなセントラリティの分散型革命を今後も見守っていきたい。